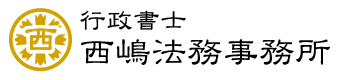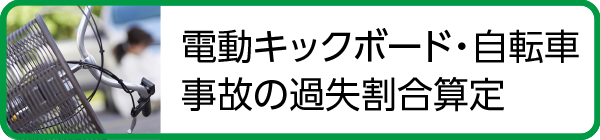
早期の事実確認が重要
判例に基づく認定過失要素・判断材料等に基づき、早期段階の事実確認による重要要素の確定で依頼者のお手伝いをいたします。
自転車事故による高額な損害賠償事例の増加により「10%の過失修正」だけでも大きな影響が出ます。
泣き寝入りとならぬよう一般的・基本的な過失割合の算定手順を確認し、どのような点に注意すべきかなど知っておきましょう。
過失割合の算定手順
- まず、事故態様から下記のいずれかの過失相殺率の認定基準等を用いて基本過失割合を決定する。
・ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ)
・ 交通事故損害額算定基準(青い本)
・ 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本) - 次に、当事者の過失要素による修正をする(ここまでが基本算定)。
たとえば、速度違反や徐行義務違反、著しい過失や重過失といった修正要素があります。 - 交通事故の発生状況による個別の過失修正をする。
なお、裁判例にある「事故態様における過失割合」が絶対ではありませんので注意が必要です。
個別の事故における事実、特に【社会問題化している行為態様】等によっては、過失割合が変わってくることとなります。
たとえば前方不注視。
事故直前における不注意が原因の場合とスマホ使用等のながら運転が原因による場合では、その危険性の度合いなども考慮される場合があります。
著しい過失や重過失などの過失修正要素を掘り下げることで、過失割合に大きな影響が生じることとなるので注意が必要です。
過失割合に納得がいかない場合には、事故発生状況の整理・検討の際の注意点等も確認するようにしましょう。
判例の過失相殺の注意点
過失割合について判例を利用する場合、その過失判断・事実認定を明確にしなければなりません。
切り取られた一場面があなたの事故と同様の発生状況であっったとしても、他の条件が異なれば過失割合は大きく変わる場合があります。
例えば、自転車同士の事故の場合には「軽車両同士の事故」ということで、基本的には「四輪車 対 四輪車」の過失割合の算定基準を準用します。
しかし、四輪車 対 四輪車の過失割合の算定基準を用いることが明らかに間違いの場合もありますので注意が必要です。
例:十字路・T字路・丁字路などの交差点における自転車同士の出会い頭の事故
故なき過失を押し付けられてはいないかなど、しっかりと確認することが大切です。
過失割合の変更
判例と同類型の事故態様に基づく過失割合に関しては、その変更を申し立てることが可能です。
その理由として下記のようなことが挙げられます。
- 裁判においては、個別の事件における「裁判官が認定した事実」に基づいて判決がなされること。
- 裁判官の思考方法として、基本的に、まず動かし難い事実を決めてから経験則で仮説を立て、証拠で裏付けるという方法(経験則に反する場合はその主張立証が必要)を取っていること。
そのため、挙証責任のある原告の主張立証・説明等が上手くいかないと不利益を被ることになります。 - 裁判所は、当事者の主張していないことを判決の基礎にできないということ。
つまり、判例において「過失認定の際に考慮されていないものが多々ある」ということです。
上記を踏まえて事故発生状況・事実関係等を整理しておけば、示談段階で相手方・保険会社等が提示する過失割合の綻びをつくことができます。
過失の定義等は判例等によって確立していますので、個別の事件・事故においては下記のことが重要になります。
- 事件・事故発生状況を的確に把握し、客観的・主観的・状況等の証拠、実情、経験則等、明確な根拠を基に事実関係を整理する。
- 過失要素を細分化して、過失の程度の差を明確にする。
- 第三者にも分かり易く、事故発生状況に即した効果的な表現を用いる。
注意点としては、事故態様によって着目すべきポイントが変化することです。
自転車事故で揉めてしまって裁判所のご厄介になった場合には、被害者が加害者の不法行為責任について主張・立証しなければなりません。
その際、相手方の過失を完璧に立証する必要はありません。
裁判長に「なるほど、確かにそうかもしれないな。」といった心証を持ってもらえれば、相手方の過失を認めてもらえる可能性があります。
これは、自由心証主義によります。
民事訴訟法第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
相手方保険会社・弁護士から提示された過失割合に対して異議申立をした際に、
「あなたがそれを事実だと主張するのなら、『合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証』か『合理的な疑いを超える証明』が必要です。」
などと言われることがありますが、民事訴訟の場合の必要な証明の程度は、下記のように刑事訴訟よりも緩やかな基準になっています。
昭和50年10月24日最高裁判決「必要な証明の程度」
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
事故や事件に遭った際には必ず最悪の場合を想定しておくべきです。
相手があまりに不誠実で平気で嘘を吐く輩の場合には、徹底抗戦する覚悟を持たなければなりません。自身のみならず、大切な家族のためにもです。
さて、著しい過失や重過失といった一般的過失修正要素は通常予定されているものですから、それを考慮して過失相殺を行うのは当然のことです。
過失の加算要素を相手方や第三者に説明等する際は、しっかりとした根拠を示す方がより効果的です。
そのため、自転車事故の事故発生状況・現場等から過失要素を細分化して個別に検討・調整を繰り返し、ランク分けを行って適正な過失修正表等を作成することをお勧めします。
相手方の過失が明確となる他、あなた自身の過失に気付くこともできるでしょう。なお、自身に過失がある場合には「認めるべきところは認め、誠意をもって謝る」ことが大切です。
自転車事故過失修正要素
自転車事故における過失要素とその修正値に関して主なものを以下に列挙しますが、あくまでも目安でありこれが絶対という訳ではありません。
なお、過失修正が問題になるのは、それが事故発生原因や被害の拡大等について相当因果関係がある場合に限られますので注意が必要です。
過失修正値に幅があるのは、個別の事故において当事者の過失の程度に「差」が生じるからです。
過失の程度に関しては、過失修正要素の細分化検討によるランク分けを行うことで明確にできます。過失の修正値が最大になるような場合は、過失要素が重複した場合や程度が著しい場合、または故意・危険な状態を認容していた場合などとお考えください。
| 行為態様 | 修正値 |
| ながら運転・スマホ利用等 | 10~30 |
| ながら運転・ヘッドホン等使用 | 10~20 |
| 夜間無灯火 | 10~20 |
| 二人乗り・曲乗り運転等 | 10~30 |
| 高速度・スピードの出し過ぎ | 10~30 |
| 酒気帯び・酒酔い・飲酒運転等 | 10~30 |
| あおり運転 | 100 |
| 徐行義務違反 | 10~20 |
| 片手運転・傘差し運転・買い物袋をハンドルに掛けた運転 | 10~30 |
| 傘固定具使用 | 5~10 |
| 犬の散歩(犬の大きさも考慮する) | 20~30 |
| 前方不注視・低視力・視野狭窄 | 5~30 |
| 整備不良・違法改造 | 5~30 |
| サイズ不一致・体格不適合・サドルが高く足が届かない等 | 5~20 |
| 警音器(ベル)の使用・不使用 | 5~20 |
| 飛び出し ※ 歩行者の「飛び出し」が問題となる場合は「小走り以上の速度」を考えます。通常の歩行速度の場合には「進出」ということになります。 | 10~30 |